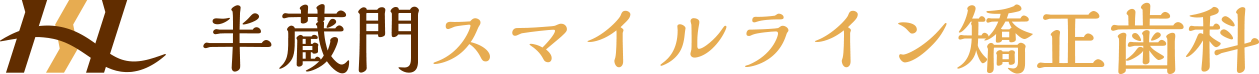広く知られている
唇側(表側)ブラケット矯正装置
(ラビアルブラケット矯正装置)
Labial
広く知られている
唇側(表側)ブラケット矯正装置
(ラビアルブラケット矯正装置)
Labial

上下の歯とも舌側(裏側)にブラケット矯正装置を装着する舌側(裏側)ブラケット矯正装置(フルリンガルブラケット矯正装置)に対して、上下の歯とも唇側(表側)にブラケット矯正装置を装着して歯並びを整える矯正装置です。
矯正装置の中では、歴史が長く、現在でもワイヤーによる矯正治療の主流となっています。
そのため不正咬合の適応症例は広くて、年齢に関係なく治療ができます。ブラケットは金属製の他、乳白色や透明の目立ちにくい材質のものもあり、舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)より治療費を抑えることができます。
なお、当院では金属アレルギーの方でもワイヤーによる矯正治療をお受け頂けます様、ニッケルを含まないワイヤーをオプションとしてご用意しております。
唇側(表側)ブラケット矯正装置
(ラビアルブラケット矯正装置)の
メリット
適応症例が広くて年齢を選ばない
矯正治療の中では歴史が長く、現在でもワイヤーによる矯正治療の主流であるため、乳歯列を除いて年齢に関係なく、また歯並びや噛み合わせに関係なくほとんどの不正咬合に対応できます。
発音や咀嚼、嚥下への影響が小さい
舌が直接触れる歯の舌側(裏側)にブラケット矯正装置を装着する舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)と異なり、歯の唇側(表側)にブラケット矯正装置を装着するため、口唇や頬粘膜にブラケット矯正装置が触れることに慣れてしまえば、発音や咀嚼、嚥下などの舌の働きへの影響は小さいと考えます。
舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)よりも治療費を抑えられる
唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)は現在でもワイヤーによる矯正治療の主流で、矯正装置としては一般的であるため、マウスピース型矯正歯科装置によっては、また舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)よりも治療費を抑えられます。
舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)よりも治療期間が短くなる場合がある
唇側(表側)のブラケット矯正装置は舌側(裏側)のブラケット矯正装置よりもブラケット間距離が長いため、歯並びを整えるための硬くて太いワイヤーへの交換がスムーズになるため、デコボコなどの歯並び状態によっては、舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)よりも治療期間が短くなる場合があります。
また、歯はブラケットが接着している方向へ移動しやすいという特性があるため、唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)は歯の唇側(表側)へ移動しやすく、デコボコの歯並びの改善がしやすく治療期間が短くなる場合があります。
舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)よりも歯磨きがしやすい。
固定式の矯正装置は、可撤式と異なり食事や歯磨きがしにくくなりますが、歯の唇側(表側)にブラケット矯正装置を装着する唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)は、舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)に比べて視認性が高く歯磨きの際、磨き残しの確認がしやすい。
唇側(表側)ブラケット矯正装置
(ラビアルブラケット矯正装置)の
デメリット
装置が見えるため見た目のストレスになる場合がある
上下の歯とも唇側(表側)にブラケット矯正装置を装着するため、見た目を気にされる方は心理的なストレスを抱える場合がございます。
当院では、そのような方のために乳白色や透明の目立ちにくい材質のブラケットに白色の金属(ロジウム)をコーティングしたワイヤー(ホワイトワイヤー)を組み合わせたオプションをご用意しており、装置の見た目による動的治療中の心理的ご負担は軽減されると考えます。
ブラケットの厚みにより口元に突出感が生じたり、助長される可能性がある
上下の歯とも唇側(表側)にブラケット矯正装置を装着するため、ブラケットの厚みの量だけ上下口唇に突出感が生じたり、上顎前突や上下顎前突などの症例では上や上下の口唇の突出感が生じたり、増幅する可能性は否定できませんが、臨床上、ブラケットの厚み程度では、口唇の厚みや口唇圧などが影響して口唇の突出感にはほとんど影響することはないと考えます。
唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)に向いている方
装置が見えることより歯並びや噛み合わせに関して質の高い治療結果を優先したい方
装置の構造上、歯の移動をコントロールしやすいため、歯並びや噛み合わせに関係なくほとんどの不正咬合に対応でき、質の高い治療結果を求める方に向いています。
装置装着による違和感、特に発音や咀嚼、嚥下などに不安のある方
歯の唇側(表側)にブラケット矯正装置を装着するため、口唇や頬粘膜に装置が触れることに慣れてしまえば、発音や咀嚼、嚥下など舌の働きへの影響は小さいと考えますので、お仕事上、接客などで話すことに携わる方の他、上顎前突や開咬などの症例で舌突出癖のある方は舌の動きを阻害しにくいと考えます。
できるだけ治療費を抑えたいという方
現在でもワイヤーによる矯正治療の主流で、矯正装置としては一般的であるため、他の矯正装置に比べて治療費が抑えられます。
ちなみに当院では装置技術調整料として装置技術料の他、毎月の通院ごとにかかる調整料を含む定額とした治療費となっておりますので、治療期間を気にせず、安心して矯正治療を始められます。
唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)に向いている方

-
装置が見えることより歯並びや咬み合わせに関して質の高い治療結果を優先したい方
装置の構造上、歯の移動をコントロールしやすいため、歯並びや咬み合わせに関係なくほとんどの不正咬合に対応でき、質の高い治療結果を求める方に向いています。
-
装置装着による違和感、特に発音や咀嚼、嚥下などが不安のある方
歯の唇側(表側)にブラケット矯正装置を装着するため、口唇や頬粘膜に装置が触れることに慣れてしまえば、発音や咀嚼、嚥下など舌の働きへの影響は小さいと考えますので、お仕事上、接客などで話すことに携わる方の他、上顎前突や開咬などの症例で舌突出癖のある方は舌の動きを阻害しにくいと考えます。
-
できるだけ治療費を抑えたいという方
現在でもワイヤーによる矯正治療の主流で、矯正装置としては一般的であるため、他の矯正装置に比べて治療費が抑えられます。
ちなみに当院では装置技術調整料として装置技術料の他、毎月の通院ごとにかかる調整料を含む定額とした治療費となっておりますので、治療期間を気にせず、安心して矯正治療を始められます。
●矯正治療に伴う一般的なリスク・副作用
- ・公的健康保険適用外の自費(自由)診療となります。
- ・矯正装置装着後は違和感、不快感、痛みなどが生じることがありますが、数日から1、2週間で慣れるのが、一般的だと考えます。
- ・歯の動き方には、個人差があるため、予定していた動的治療期間が長くなることがあります。
- ・不規則な通院、矯正装置の脱離や破損の頻発、矯正装置や保定装置などの使用協力の欠如、動的治療中のエラスティック リング(顎間ゴム)の使用協力の欠如、虫歯や歯肉炎、歯周病の要因である不適切な歯磨きやかかりつけ歯科医での定期検査の欠落による動的治療の中断など、患者様の協力が得られない場合、動的治療期間の延期、歯並びや咬み合わせの後戻りの原因となります。
- ・固定式の矯正装置を装着している場合、歯磨きがしにくく、虫歯や歯肉炎、歯周病になるリスクが高くなるので、日常的に適切な歯磨きを行う他、かかりつけ歯科医での定期検査が必要となります。
歯が動くことで、治療前の検査では確認できなかった小さな虫歯が見つかったり、親知らずや根尖病巣(歯根の先端の病変)があると炎症を起こし、歯肉が腫脹したり、痛みが出たりすることがあります。 - ・歯が動くことで、歯茎がやせてブラックトライアングルなど審美的な弊害が生じることがあります。
- ・歯が動くことで、歯根の形が丸くなったり、短かくなったり歯根吸収を起こすことがあります。
- ・外傷などの原因で歯根周囲を取り巻く歯根膜が変性してしまいますと歯を植えている歯槽骨と癒着してしまうアンキロージスを起こしてしまい、歯が動かないことがあります。
- ・歯を動かすことで歯髄内の血管や神経の損傷により壊死することで歯が黒く変色してしまうことがあります。
- ・金属アレルギーやラテックスアレルギーのある患者様は、動的治療中や保定中にアレルギー症状が出ることがあります。
- ・矯正力による機械的外力や精神的なストレスなどにより、動的治療中に顎関節や咀嚼筋が痛い、口が開きにくい、顎関節部から音がするなど顎関節症状が生じたり、ごくまれに顎関節の関節頭が吸収したり、吸収が進行することがあります。
- ・歯の形態を整えたり、歯幅の左右対称性を図るため、また咬み合わせを緊密にするために、詰め物(修復物)をしたり、許容範囲内で歯のエナメル質を削ることがあります。
- ・動的治療の経過によっては、非抜歯による治療から抜歯による治療に変更したり、付加装置などを追加・変更するなど当初予定していた治療計画を変更することがあります。
- ・動的治療中に矯正装置の一部、器具を誤飲することがあります。
- ・固定式の矯正装置を撤去するにあたり、エナメル質が剝がれたり、表面に微小な亀裂が生じたり、詰め物(修復物)や被せ物(補綴物)の一部が破損することがあります。
- ・永久歯が先天性欠如している場合、歯数を合わせるため抜歯による治療を行ったり、将来的にインプラントを埋入したり、義歯やブリッジなどの被せ物(補綴物)を装着する前提で隙間を作り、審美的・機能的回復を図ることがあります。
また動的治療開始前に歯幅の調和がとれてない被せ物(補綴物)を仮歯に置き換えたり、ブリッジ(補綴物)のダミー部を撤去した状態で動的治療を行い、動的治療終了後に被せ物(補綴物)をやり直したり、義歯を入れたり、インプラントを埋入することがあります。 - ・動的治療が終了し矯正装置の撤去後、可撤式の保定装置については指示通りの使用協力がないと、歯並びや咬み合わせが後戻りすることがあります。
- ・顎の成長発育、加齢や歯周病などにより、歯並びや咬み合わせが変化することがあります。また加齢により、ほうれい線が生じると考えらえています。
- ・動的治療終了後に親知らずの影響で、歯並びや咬み合わせが変化することがあります。
- ・矯正治療を一度開始すると元の歯並びや咬み合わせには戻すことは難しくなります。
- ・矯正治療により上下の前歯を前方や後方へ傾斜することにより、上下口唇の突出感が生じたり、増幅したりする一方、陥凹感が生じたり、増幅するなど変化することがありますが、矯正歯科医師による側貌のコントロールはできません。
- ・治療期間は歯並びと咬み合わせに異なりますが、前歯だけ永久歯に生え揃う小学校低学年(1〜4年生頃)の混合歯列で第一期矯正治療(限局矯正)を行う必要がある場合、動的治療期間は約半年~1年半程度ですが、その後、全ての歯が永久歯に生え揃う永久歯列で第二期矯正治療として広範囲矯正治療(本格矯正)が必要になった場合、成人矯正同様、動的治療期間は約1年半〜2年半程度ですが、2年半以上要することもあり、通院期間は総じて10年以上に及ぶことになります。
●矯正歯科治療について
1.公的健康保険適用外の自費(自由)診療になります。
2.矯正治療の通院期間は歯並びを整える動的治療期間とその後、整えた歯並びが後戻りしない様に保定装置(リテーナー)を装着して頂きながら経過観察を行う保定期間の合計となります。
3.矯正治療の治療期間や通院回数は矯正治療の開始時期、不正咬合の程度、非抜歯・抜歯、使用装置などにより変わりますが、おおよその目安は以下の通りです。
- ▼混合歯列での第一期矯正治療(限局矯正)、永久歯列での部分矯正(MTM)を行った場合
- ・動的治療期間:約6か月~1年6か月、通院回数(毎月1回):約 6~18回
- ・保定期間:約1年、通院回数(数か月に1回):約4回(※1)
- ・合計通院回数:約1年6か月~2年6か月、合計通院回数:約10~22回
- ▼永久歯列での第二期矯正治療(本格矯正)を唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)にて行った場合(※2)
- ・歯を抜かない非抜歯治療での動的治療期間:約1年6か月~2年、通院回数(毎月1回):約18~24回
- ・歯を抜いた抜歯治療での動的治療期間:約2年~2年6か月、通院回数(毎月1回):約 24~30回
- ・保定期間(※3):3年、通院回数(数か月に1回):約12回
- ・合計通院回数:約4年6か月~5年6か月、合計通院回数:約30~42回
※1 混合歯列で第一期矯正治療(限局矯正)を行った場合、約1年間の保定期間終了後も永久歯列完成まで経過観察を継続しますので、通院回数は4回以上になります。
※2 舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)の場合、唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)よりも動的治療期間が長くなる場合があります。
※3 当院が規定する保定期間と通院回数で記載しております。