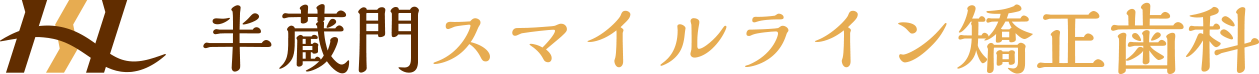当院の矯正治療の流れ
Flow
当院の矯正治療の流れ Flow
永久歯列の矯正治療につきまして当院の矯正治療の流れをご説明致します。
-
STEP
01
初診相談
所要時間30〜90分
ご来院後、健康記録の他、ご記入して頂いた当院オリジナルのヒアリングシートから患者様の気になる点、ご不安・ご不明な点、ご希望の矯正装置の有無などを把握させて頂きながら、歯並びについての問診・視診、口元の突出感の有無や程度、口腔機能、姿勢などの観察を通して、治療の方針・期間・費用・流れなどの概略についてご説明させて頂きます。当院では、マンツーマンでじっくりとお話を伺いながらご納得いくまでご説明させて頂く体制をとっており長年の臨床経験から様々ご提案ができるかと思います。
所要時間の目安は永久歯列で約90分、乳歯列や混合歯列、セカンドオピニオンでは約30分となります。
-
STEP
02
治療前検査
所要時間120分
矯正を始めるということになりますと治療計画を立てなくてはなりません。その際、各種分析結果が必要になるため、初診時の矯正治療に関する患者様情報を踏まえた上で、まずは精密検査を行います。
当院では日本矯正歯科学会の規定に沿った顔面・口腔内写真撮影、X線撮影(パノラマ、セファロ、デンタル、顎関節など)、軟組織検査、歯列模型を製作するための歯型採りを行います。
また、子供の場合、成長発育に関わる治療になるため、身長・体重測定、手根骨のX線写真撮影を追加することもあります。
ちなみに、セファロ・模型の分析結果につきましては、母校で使用している分析ソフトを活用しております。
-
STEP
03
診断
所要時間60〜120分
診断では今後の矯正治療に関わるすべての内容の詳細をお話させて頂く大事なステップになります。
当院の診断では以下のとおり重要な3項目につきまして十分にご説明させて頂いた上で、書類にてお渡しし、ご承諾を頂いた上で治療開始というステップを踏んでおります。- 1.精密検査による各種分析結果を写真・表にした書類の他、分析結果を踏まえた治療計画書のお渡し。
- 2.日本矯正歯科学会の「矯正治療に関わるリスク・副作用」に加え、約30項目の当院オリジナルのご承諾書のお渡し。
- 3.使用する矯正装置、使用する保定装置、動的治療・保定期間、お支払い方法(キャッシュ、キャッシュお振込、クレジット、デンタルローン)・回数など記載した「お支払い確認書」のお渡し。
その他、矯正治療を行うにあたり付加装置が必要になる可能性がある場合、付加装置別に注意事項が異なりますので、装着する装置の注意事項をご説明させて頂いた上で書類にてお渡ししております。
所要時間の目安は永久歯列で約120分、乳歯列や混合歯列、部分矯正(MTM)、セカンドオピニオンでは約60分となります。
お渡しした「矯正治療に関わるリスク・副作用」の内容につきましては、ご理解・ご承諾の上、ご捺印を添えてご署名を頂き、「お支払い確認書」につきましては、記載されている色々なお支払い方法・回数の中から、ご希望の方法・回数をご検討の上、必要事項をご記入の上、ご捺印を添えてご署名を頂き、後日これらの書類をご持参して頂きます。
-
STEP
04
書類の取り交わし
所要時間30分
以下の通り診断時にお渡しした書類をご持参して頂き、それら書類に当院の方でも捺印後、コピーをお渡しします。
- 1.ご捺印を添えてご署名のある「矯正治療に関わる同意書」
- 2.ご検討頂きました色々なお支払い方法・回数、必要事項をご記入の上、ご捺印を添えてご署名のある「お支払い確認書」
上記の書類の取り交わしをもって治療開始とさせて頂いております。

-
STEP
05
矯正治療を開始する前に必要な前処置
虫歯や歯周病、顎関節症などの治療が必要な場合や親知らずに炎症がある場合、矯正装置装着前に治療します。
また、被せ物(補綴物)については治療後に再製が必要な場合がありますが、歯の移動が必要なブリッジがある場合には、装置装着前に切断、治療後に再製します。また、永久歯列の抜歯治療では、通常、装置装着前に行いますが、当院では抜歯部位を見極めるために装置装着後に行います。
また、非抜歯治療か抜歯治療か判断しにくい場合や咬み合わせが不安定で抜歯部位の見極めが難しい場合、コンピュター上で装置製作が必要なマウスピース型矯正歯科装置(インビザライン)、カスタムメイド舌側ブラケット矯正装置(インコグニート)でも、装置装着後に抜歯となります。
-
STEP
06
矯正装置の装着
所要時間60〜120分
通常、装置装着後から違和感、また数日間、矯正力による歯の痛みが生じますので、できるだけご負担を軽減するために原則、まずは歯のクリーニングから行い、上の歯並びから装置を装着しますが、下の歯並びへの装着は数か月後になります。装置装着後は、歯の動揺、口内炎などの粘膜の炎症、食事の仕方・食べ物などに関する注意点、ブラッシング方法など装置装着後の注意事項などをご説明させて頂き書類にてお渡しします。所要時間の目安は、混合歯列、部分矯正(MTM)で約60分、永久歯列の場合、唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)で90分、舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)では120分と装置の種類や装着範囲により異なります。

-
STEP
07
調整
所要時間60〜90分
装置装着後は歯並びを整えるまで約3〜4週間に1回の間隔で通院して頂きます。
通常、歯並びを整える動的治療期間は混合歯列、部分矯正(MTM)で約6か月〜1年6か月、永久歯列では唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)の場合、非抜歯治療で約年6か月〜2年、2〜4本程度の通常の抜歯治療では約2年〜2年6か月となりますが、舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)や6本以上の多数歯抜歯治療では、治療期間はそれより長くなる場合があります。
当院では矯正治療の他、歯のクリーニングや虫歯のチェックも行いますので、所要時間の目安は、混合歯列、部分矯正(MTM)で約30分、永久歯列では唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)で約60分、舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)では約90分と装置の種類や装着範囲により異なります。
-
STEP
08
抜歯治療での抜歯
所要時間60分
非抜歯治療、抜歯治療とも装置装着時は、細くて柔らかいワイヤーを上下の歯並びに使用しますが、歯並びの変化に合わせて、硬くて太くて硬いワイヤーを装着できる様になります。この時期になりますと抜歯治療では、再度、抜歯部位・本数を確認、ご説明させて頂き抜歯に移行します。
通常、当院で抜歯をされる患者様の場合、1本ずつ分けて行っており、抜歯後は止血の確認のため20分程度、安静にして頂き体調が落ち着き次第、お帰り頂いております。
-
STEP
09
調整の継続
所要時間60〜90分
前述した通り非抜歯治療、抜歯治療とも装置装着時は、細くて柔らかいワイヤーを上下の歯並びに使用しますが、歯並びの変化に合わせて、硬くて太くて硬いワイヤーが装着できる様になります。非抜歯治療は、さらにワイヤーの交換と調整を続けながら歯並びの仕上げに移行しますが、抜歯治療では抜歯したスぺースを利用して歯の移動を行った後、抜歯スペースの完全閉鎖、歯並びの仕上げに移行します。

-
STEP
10
矯正装置撤去ならびに保定装置(リテーナー)装着
所要時間60分
歯並びが整い咬み合わせが治りますと、後戻りを防ぐ保定装置製作のため、歯型採りを行います。
原則、取り外しできる保定装置になりますが、保定力の効果がそれでは不十分であると判断した場合、歯の裏側に固定式の保定装置を併用または変更する場合があります。
なお、当院の保定管理する保定期間は保定装置を装着した月から起算して、乳歯列、混合歯列、部分矯正(MTM)で1年間、広範囲矯正治療(本格矯正)では3年間としています。
-
STEP
11
動的治療終了後の検査
所要時間90分
治療後の評価を行うために、治療前に行った同じ内容の検査を行います。
矯正装置撤去ならびに保定装置装着日に治療後の精密検査も行うことがあります。
-
STEP
12
保定観察
所要時間30分
保定装置装着後は約4か月に1回の間隔で通院して頂きます。当院では、歯のクリーニングや虫歯のチェックを行いながら、取り外しできる保定装置は、装置のクリーニングの他、ワイヤー部のゆがみの調整、プラスチック部の破折の有無、固定式保定装置では、脱離や破損箇所の有無などの確認を行います。
なお、矯正治療後にホワイトニングをご希望される方は、この保定期間中にオフィスホワイトニングを行います。
-
STEP
13
保定2年時の検査
所要時間90分
当院では日本矯正歯科学会の規定に沿って、動的治療開始前、動的治療終了時同様、保定2年経過時にも精密検査を行い歯並びの再評価を行います。
つまり永久歯列の矯正治療は、通院中に計3回の検査、混合歯列で第一期矯正治療(限局矯正)を行った場合、動的治療前後で2回、さらに永久歯列で第二期矯正治療(本格矯正)が必要になった場合、動的治療前後で2回、さらに保定2年経過時に行いますので、計5回の検査を行います。
-
STEP
14
通院終了
所要時間30分
整えた歯並びと咬み合わせが後戻りしない様に当院が保定管理する保定期間は保定装置を装着した月から起算して乳歯列、混合歯列、部分矯正(MTM)で1年間、広範囲矯正治療(本格矯正)では3年間としています。
乳歯列、混合歯列は、永久歯列での広範囲矯正治療(本格矯正)が必要となる可能性があるため、少なくとも永久歯列完成までは通院して頂きます。
永久歯列での部分矯正(MTM)、広範囲矯正治療(本格矯正)では当院が規定する上記の保定期間を迎えますと通院終了となりますが、その後も後戻りへの不安から、ご来院を希望される患者様には、無期限で歯並びと咬み合わせに対するメンテナンスを続けて頂けます。

患者様のニーズに合った治療方法と装置の選択
当院では、従来の唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)の他、日々進歩する舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)やマウスピース型矯正歯科装置(インビザライン) アライナー型矯正歯科装置(アソアライナー)による治療にもご対応しております。
これまで培ってきた30年の長きにわたる臨床経験と、丁寧なカウンセリングや徹底したインフォームドコンセント(説明と同意)の基づき、患者様お一人おひとりの歯並びや咬み合わせの状態とニーズに応じた治療方法のご提案や矯正装置のご提供ができればと思っております。
矯正治療ができるかどうかご心配な方から、ご自身の歯並びや咬み合わせが気になるという方、矯正治療に関しまして疑問やご不安などがある方など、是非、当院までお気軽にご相談下さい。

大人の矯正と子供の矯正治療の違い
伸び盛りの時期に入る小学校高学年から身長と体重が増加するとともに上下の顎、特に下の顎が成長します。その成長をきっかけに上下の顎の位置関係がズレたり、既に成長期前からズレがあるため、そのズレが大きくなる可能性がある場合、小学校低学年(1〜4年生頃)のうちに、上下の顎のズレが生じないように予防したり、そのズレが大きくならない様に成長の量や方向をコントロールする必要があります。
上下の顎にズレがありますと、それぞれの顎に植わっている上と下の歯並びを整える矯正治療が難しくなるからです。
小学校低学年(1〜4年生頃)に第一期矯正治療(限局矯正)を行う目的の一つは、上下の顎の位置関係がズレない様にコントロールしたり、ズレが大きくならない様に上下の顎の成長の量や方向をコントロールすることにあります。
もう一つの目的は、上下の顎の正しい成長や歯並びや咬み合わせに悪影響を及ぼすと考えられる口呼吸、舌が前に出る、指しゃぶり、唇や爪を咬むなどの口腔習癖やうつ伏せ寝や頬杖など姿勢に関わる癖がある場合、この時期に改善しておく必要があります。
口腔習癖を放置しておくと永久歯列で行う第二期矯正治療(本格矯正)では改善しにくくなったり、成長をきっかけに姿勢に関わる癖により上下の顎の位置関係がズレたりする場合があるからです。
第一期矯正治療(限局矯正)の後、永久歯に生え揃う小学校高学年(6年生頃)以降は、第二期矯正治療として広範囲矯正治療(本格矯正)を行い、大人の矯正治療同様、歯並びを整えます。
この様に上下の顎のコントロールをしたり、口腔習癖を改善する必要がある場合、永久歯列の矯正治療をより行いやすい環境を作るために、第一期矯正治療(限局矯正)として小学校低学年(1〜4年生頃)に行う訳ですが、小学校低学年(1〜4年生頃)に第一期矯正治療(限局矯正)の必要がない場合、永久歯に生え揃う小学校高学年(6年生頃)以降まで待ってから、広範囲矯正治療(本格矯正)を行う場合もあります。
なお、第一期矯正治療(限局矯正)を行った結果、第二期矯正治療(本格矯正)を行う必要がなくなる場合や広範囲矯正治療(本格矯正)ではなく、部分矯正(MTM)で済む場合もあります。
上下の顎の位置関係のズレが大きい上顎前突や下顎前突の他、重度の叢生(デコボコ)などの場合、大人の矯正治療では子供の矯正治療と異なり上下の顎の成長がないため、歯並びを整え咬み合わせ治すにあたり、永久歯のスペースを利用して歯の移動を行わなくてはならない抜歯治療の頻度が高くなります。
稀ですが、抜歯したスペースだけでは、歯並びや咬み合わせの改善が難しい程、上下の顎の位置関係のズレが重度の場合、外科手術を併用した矯正治療を行う場合もあります。
大人の矯正治療の場合、治療に対する目的意識が明確である上、上下の顎の予期せぬ成長がないため、治療結果が予測しやすく、使用できる矯正装置も多岐にわたるという点で子供の矯正治療とは大きく異なります。
●矯正治療に伴う一般的なリスク・副作用
- ・公的健康保険適用外の自費(自由)診療となります。
- ・矯正装置装着後は違和感、不快感、痛みなどが生じることがありますが、数日から1、2週間で慣れるのが、一般的だと考えます。
- ・歯の動き方には、個人差があるため、予定していた動的治療期間が長くなることがあります。
- ・不規則な通院、矯正装置の脱離や破損の頻発、矯正装置や保定装置などの使用協力の欠如、動的治療中のエラスティック リング(顎間ゴム)の使用協力の欠如、虫歯や歯肉炎、歯周病の要因である不適切な歯磨きやかかりつけ歯科医での定期検査の欠落による動的治療の中断など、患者様の協力が得られない場合、動的治療期間の延期、歯並びや咬み合わせの後戻りの原因となります。
- ・固定式の矯正装置を装着している場合、歯磨きがしにくく、虫歯や歯肉炎、歯周病になるリスクが高くなるので、日常的に適切な歯磨きを行う他、かかりつけ歯科医での定期検査が必要となります。
歯が動くことで、治療前の検査では確認できなかった小さな虫歯が見つかったり、親知らずや根尖病巣(歯根の先端の病変)があると炎症を起こし、歯肉が腫脹したり、痛みが出たりすることがあります。 - ・歯が動くことで、歯茎がやせてブラックトライアングルなど審美的な弊害が生じることがあります。
- ・歯が動くことで、歯根の形が丸くなったり、短かくなったり歯根吸収を起こすことがあります。
- ・外傷などの原因で歯根周囲を取り巻く歯根膜が変性してしまいますと歯を植えている歯槽骨と癒着してしまうアンキロージスを起こしてしまい、歯が動かないことがあります。
- ・歯を動かすことで歯髄内の血管や神経の損傷により壊死することで歯が黒く変色してしまうことがあります。
- ・金属アレルギーやラテックスアレルギーのある患者様は、動的治療中や保定中にアレルギー症状が出ることがあります。
- ・矯正力による機械的外力や精神的なストレスなどにより、動的治療中に顎関節や咀嚼筋が痛い、口が開きにくい、顎関節部から音がするなど顎関節症状が生じたり、ごくまれに顎関節の関節頭が吸収したり、吸収が進行することがあります。
- ・歯の形態を整えたり、歯幅の左右対称性を図るため、また咬み合わせを緊密にするために、詰め物(修復物)をしたり、許容範囲内で歯のエナメル質を削ることがあります。
- ・動的治療の経過によっては、非抜歯による治療から抜歯による治療に変更したり、付加装置などを追加・変更するなど当初予定していた治療計画を変更することがあります。
- ・動的治療中に矯正装置の一部、器具を誤飲することがあります。
- ・固定式の矯正装置を撤去するにあたり、エナメル質が剝がれたり、表面に微小な亀裂が生じたり、詰め物(修復物)や被せ物(補綴物)の一部が破損することがあります。
- ・永久歯が先天性欠如している場合、歯数を合わせるため抜歯による治療を行ったり、将来的にインプラントを埋入したり、義歯やブリッジなどの被せ物(補綴物)を装着する前提で隙間を作り、審美的・機能的回復を図ることがあります。
また動的治療開始前に歯幅の調和がとれてない被せ物(補綴物)を仮歯に置き換えたり、ブリッジ(補綴物)のダミー部を撤去した状態で動的治療を行い、動的治療終了後に被せ物(補綴物)をやり直したり、義歯を入れたり、インプラントを埋入することがあります。 - ・動的治療が終了し矯正装置の撤去後、可撤式の保定装置については指示通りの使用協力がないと、歯並びや咬み合わせが後戻りすることがあります。
- ・顎の成長発育、加齢や歯周病などにより、歯並びや咬み合わせが変化することがあります。また加齢により、ほうれい線が生じると考えらえています。
- ・動的治療終了後に親知らずの影響で、歯並びや咬み合わせが変化することがあります。
- ・矯正治療を一度開始すると元の歯並びや咬み合わせには戻すことは難しくなります。
- ・矯正治療により上下の前歯を前方や後方へ傾斜することにより、上下口唇の突出感が生じたり、増幅したりする一方、陥凹感が生じたり、増幅するなど変化することがありますが、矯正歯科医師による側貌のコントロールはできません。
- ・治療期間は歯並びと咬み合わせに異なりますが、前歯だけ永久歯に生え揃う小学校低学年(1〜4年生頃)の混合歯列で第一期矯正治療(限局矯正)を行う必要がある場合、動的治療期間は約半年~1年半程度ですが、その後、全ての歯が永久歯に生え揃う永久歯列で第二期矯正治療として広範囲矯正治療(本格矯正)が必要になった場合、成人矯正同様、動的治療期間は約1年半〜2年半程度ですが、2年半以上要することもあり、通院期間は総じて10年以上に及ぶことになります。
●矯正歯科治療について
1.公的健康保険適用外の自費(自由)診療になります。
2.矯正治療の通院期間は歯並びを整える動的治療期間とその後、整えた歯並びが後戻りしない様に保定装置(リテーナー)を装着して頂きながら経過観察を行う保定期間の合計となります。
3.矯正治療の治療期間や通院回数は矯正治療の開始時期、不正咬合の程度、非抜歯・抜歯、使用装置などにより変わりますが、おおよその目安は以下の通りです。
- ▼混合歯列での第一期矯正治療(限局矯正)、永久歯列での部分矯正(MTM)を行った場合
- ・動的治療期間:約6か月~1年6か月、通院回数(毎月1回):約 6~18回
- ・保定期間:約1年、通院回数(数か月に1回):約4回(※1)
- ・合計通院回数:約1年6か月~2年6か月、合計通院回数:約10~22回
- ▼永久歯列での第二期矯正治療(本格矯正)を唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)にて行った場合(※2)
- ・歯を抜かない非抜歯治療での動的治療期間:約1年6か月~2年、通院回数(毎月1回):約18~24回
- ・歯を抜いた抜歯治療での動的治療期間:約2年~2年6か月、通院回数(毎月1回):約 24~30回
- ・保定期間(※3):3年、通院回数(数か月に1回):約12回
- ・合計通院回数:約4年6か月~5年6か月、合計通院回数:約30~42回
※1 混合歯列で第一期矯正治療(限局矯正)を行った場合、約1年間の保定期間終了後も永久歯列完成まで経過観察を継続しますので、通院回数は4回以上になります。
※2 舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)の場合、唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)よりも動的治療期間が長くなる場合があります。
※3 当院が規定する保定期間と通院回数で記載しております。
●マウスピース型矯正歯科装置による治療に伴う一般的なリスク・副作用
- ・マウスピース型矯正歯科装置(インビザライン)、アライナー型矯正歯科装置(アソアライナー)などは、取り外しができる反面、破損や紛失することがあります。
- ・マウスピース型矯正歯科装置(インビザライン)、アライナー型矯正歯科装置(アソアライナー)などは、ブラケット矯正装置より適応症例が狭く、治療期間が長くなることがあるため、ワイヤーによる矯正装置と併用することがあります。
- ・厚みが薄いマウスピース型矯正歯科装置(インビザライン)、アライナー型矯正歯科装置(アソアライナー)などでも直接、舌が触れるため、発音については多かれ少なかれ影響があると考えますが、固定式の矯正装置や保定装置同様、一般的に数日から1、2週間で軽減します。
- ・マウスピース型矯正歯科装置(インビザライン)は毎日20時間以上、アライナー型矯正歯科装置(アソアライナー)では毎日17時間以上の装着を目安として、歯並びが整うまでマウスピースを嵌め変えますが、適切な装着を継続しないと歯並び自体にゆがみが生じることがあります。
- ・マウスピース型矯正歯科装置(インビザライン)は、歯の唇側(表側)にアタッチメント(乳白色の光で硬化する突起)を接着する場合があります。
- ・マウスピース型矯正歯科装置(インビザライン)は、コンピューター上で設計された歯並びの完成形までのすべてのマウスピースが製作されるため、破損や紛失した場合も含めて、動的治療中や保定中に虫歯などで詰め物(修復物)や被せ物(補綴物)により、歯の形が変わってしまった場合、既存のマウスピースが適合しなくなるため、改めて作り直すことになります。
- ・アライナー型矯正歯科装置(アソアライナー)は、歯の生え代わりや顎の成長などお口の中が変化しても、詰め物(修復物)や被せ物(補綴物)により歯の形が変わっても、その都度、歯型を採ってマウスピースを製作するので、マウスピース型矯正歯科装置(インビザライン)と異なり、より正確で再現性の高いマウスピースによる効率的な治療が期待できる反面、術者の手間と患者様のご負担が掛かかります。
- ・マウスピース型矯正歯科装置(インビザライン)では、歯並びの完成形までのすべてのマウスピースが作られるため、歯の生え代わりや顎の成長などお口の中の変化に合わせた作り直しができないため、治療開始年齢は顎の成長や歯の生え代わりなどが落ち着きお口の中が安定するほぼ永久歯列完成期からになります。
薬機法において承認されていない医療機器「マウスピース型矯正歯科装置」について
当院でご提供しているマウスピース型矯正歯科装置は、薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。
○未承認医療機器に該当
薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2023年2月14日最終確認)。
○入手経路等
装置により異なりますが、インビザライン・ジャパン株式会社、株式会社アソインターナショナルなどから入手しています。
○国内の承認医療機器等の有無
国内では、マウスピース型矯正歯科装置と同様の性能を有した承認医療機器は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2023年2月14日最終確認)
○諸外国における安全性等にかかわる情報
情報が不足しているため、ここではマウスピース型矯正歯科装置の諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。
なお、日本では完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。
※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。
●舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)による治療に伴う一般的なリスク・副作用
- ・傾斜や捩れの改善が難しいなど唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)に比べて、高度な技術が要求されるなどの理由で治療費が高額になります。
- ・唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)に比べて、硬くて太いワイヤーへの交換に時間がかかることから治療期間が長くなることがあります。
- ・歯はブラケットが接着している方向へ移動しやすいという特性から、歯の唇側(表側)への移動はしにくいという特性があります。
- ・直接、舌が触れる歯の舌側(裏側)にブラケット矯正装置がついているため、唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)に比べて、発音や咀嚼、嚥下などの舌の働きへの影響は特に大きいと考えますが、一般的に数日から1、2週間で軽減します。
- ・傾斜や捩れがある上の前歯にエラスティックチェーンを装着する目的で、また上下の前歯の咬み合わせを緊密にしたり、上下の咬み合わせの前後的なズレを修正するためのエラスティック リング(顎間ゴム)が装着できるように、付加装置として透明なアタッチメントを歯の唇側(表側)に接着することがあります。
●クリーニング・PMTCに伴う一般的なリスク・副作用
- ・公的健康保険適用とされる場合もありますが、原則、公的健康保険適用外の自費(自由)診療となります。
- ・虫歯や歯肉炎、歯周病の予防に関しては、日常生活における適切な歯磨きや定期健診が重要で、歯科クリニックで行うクリーニングやPMTCだけでは不十分であると考えます。
- ・歯肉炎や歯周病のある方は、クリーニングやPMTCに使用する器具や機材による機械的刺激により一時的に歯肉から出血することがあります。
- ・クリーニングやPMTCを行うにあたり、歯石が付着している歯につきましては歯石除去の際、一時的に歯肉から出血することがあります。
- ・着色や歯垢、歯石が付きやすい付きにくいは個人差がありますので、日常生活における適切な歯磨きの他、継続的な定期健診が重要であると考えます。